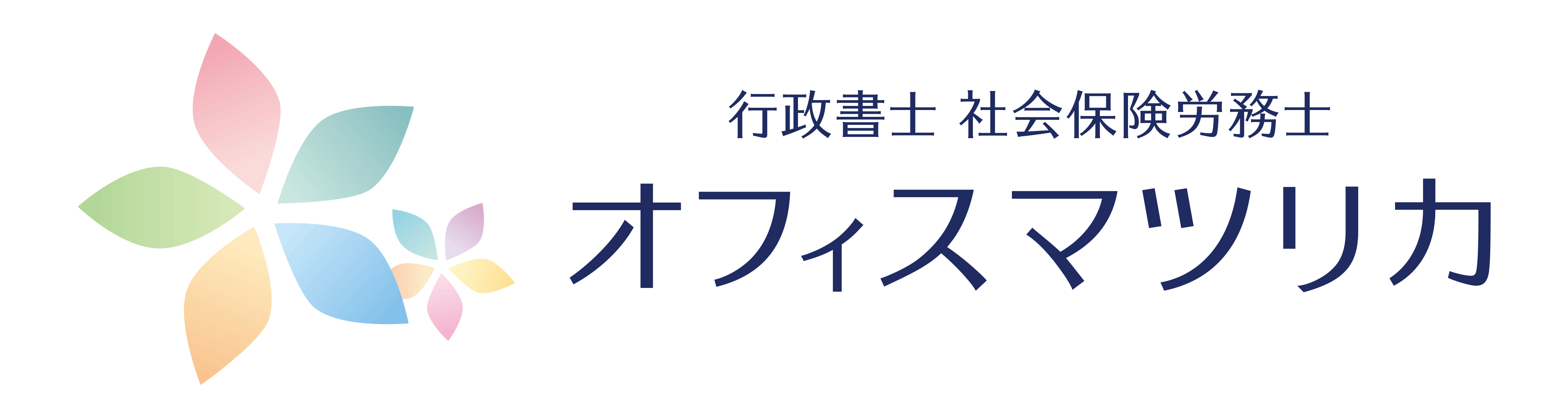建設業許可申請
建設業許可について
建設業許可制度は、建設業の適正な運営と品質の確保を目的に設けられています。
例えば、請負金額が500万円(税込)以上の工事を行う場合、建設業法により許可取得が義務付けられています。この仕組みは、依頼主が安心して工事を任せられる環境を整えると同時に、不適切な工事や契約を防ぐ役割を果たします。
建設業許可を取得することで、事業者はさまざまなメリットを享受できます。まず、公共工事への参加資格を得られるため、大規模なプロジェクトへの参入機会が広がります。さらに、許可を取得していること自体が信頼の証となり、民間企業や顧客からの信用度が向上するほか、法令を遵守している事業者として認識されることで、不適切な価格競争や法的リスクを回避できる点も重要です。
さらに、従業員の雇用や下請け業者との取引においても、許可を取得している事業者は安心感を与えることができます。建設業の許可取得は、事業拡大や信頼構築に欠かせない大きなステップと言えるでしょう。
建設業許可の種類について
大臣許可と知事許可
大臣許可は、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を構える場合に必要です。たとえば、東京都と神奈川県に営業所を持つ場合は、大臣許可を取得する必要があります。許可申請や更新は主たる営業所を管轄する地方整備局が担当します。
一方、知事許可は、1つの都道府県内でのみ営業所を設けて活動する場合に必要です。たとえば、東京都内だけで営業する場合は、東京都知事の許可を取得します。申請先は都道府県ごとに異なり、各自治体の担当窓口で受け付けています。
一般建設業と特定建設業
さらに、建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の区分があり、工事の請負方法や発注額によって取得すべき許可が異なっています。
一般建設業許可は、元請業者として下請業者を使わない場合、または下請契約の合計金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の工事を請け負う場合に必要です。中小規模の工事を中心に事業を展開する企業が多く取得する許可です。
一方、特定建設業許可は、大規模な工事を請け負い、下請契約の合計金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる場合に必要です。この許可は元請業者として、下請業者に工事を発注する企業に適しています。特定建設業許可を取得するためには、資本金や技術者の資格など、一般建設業許可よりも厳しい要件を満たす必要があります。
例えば、大規模なビル建設や公共工事を行う建設会社は特定建設業許可を取得することが一般的ですが、一方で小規模な住宅リフォーム等を専門とする会社は一般建設業許可で事業運営が可能です。
以上のように、大臣許可と知事許可、一般建設業と特定建設業は、それぞれ営業範囲や工事規模に応じた区分が設けられています。事業の計画や規模に合わせて、適切な許可を選び、手続きを進めることが重要です。不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
その他許認可申請
その他許認可手続きについて
個人や企業が行う事業に関する行政庁の許認可手続きについて、申請書類の作成・提出等のお手続きをいたします。
煩雑な書類の準備や作成をお任せいただくことでお客様は時間と労力を節約でき、本業に集中いただけます。
許認可手続き例

- 飲食業許可
- 古物商許可
- 宅建業許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 介護タクシー許可
- 風俗営業許可 など
各種契約書作成
事業活動や日常生活で生じる権利義務に関する契約書等の作成を行います。
- 業務委託契約書
- 各種売買契約書
- 各種賃貸借契約書
- 贈与契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 秘密保持契約書 など
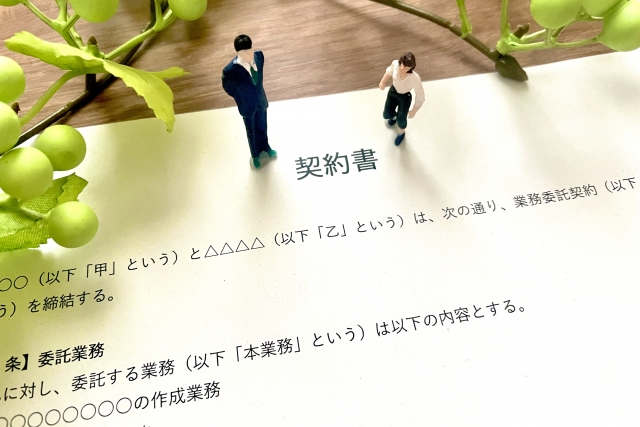
労務相談顧問 / 就業規則等作成
労務相談顧問について
貴社の顧問社労士として人事労務等に関する様々な問題についてご相談をいただけます。
いつでも気軽に話ができる相談相手としてご利用ください。
顧問契約は人事・労務相談のみの「アドバイザリー顧問契約」と労働・社会保険事務手続き、助成金のご提案・申請を含む「総合顧問契約」をご用意しております。
なお、スポット(単発)の人事・労務相談は別途有料(時間制)でお受けいたしております。
顧問契約の内容
- 人事労務に関するトラブル解決・予防
- 最新の制度説明・法改正情報の提供
- 迅速・的確な事務手続きの代行
- 各種助成金のご提案・申請書提出代行 など
就業規則・各種規定の作成
就業規則とは「労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集」とされております。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届けなければなりません(労働基準法第89条)。
就業規則に記載する内容には決まりがあり、必ず記載しなければいけない「絶対的必要記載事項」と、定めをする場合には記載しなければならない「相対的必要記載事項」があります。
これらの定めは法令や労働協約に反してはならず、また就業規則で定めた基準を下回る労働契約は、その部分について無効となってしまいます。
また、就業規則を変更する際にも従業員との後々の大きなトラブルを生む可能性があるため慎重な対応と準備が必要になることもあります。
「モデル就業規則」などを利用することで、見た目やある程度体裁の整った規則を作成することは可能ですが、上記の内容を踏まえつつ、社内の実情や法改正の内容を反映させ、いざというときに「使える」規則を作成・整備するためには労働関連法令の専門的知識をもつ我々社労士にお任せいただくのが安心です。
- 経営課題が明確になる
- 労使トラブルの防止につながる
- 正しい労務管理ができるようになる
- 社員の定着につながる
- 助成金を受給できる可能性がある

社会保険・労働保険手続きアウトソース
社会保険・労働保険手続きアウトソースについて
日々の事業活動に伴い発生する労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する事務手続きを貴社に代わって行います。必要に応じて電子申請を用い、的確・スピーディーに手続きを行います。
オフィスマツリカでは労働保険・社会保険に関する各種手続きの代行を「スポット委託」と「顧問契約」の2つのプランで代行しております。スポット委託は顧問契約不要で、必要なお手続きを必要な分だけご依頼いただけます。顧問契約プランは月ごとの人事労務アドバイザリー契約(顧問)のなかに手続代行料(一部手続きを除きます)が含まれております。貴社のシーンに合わせてご利用ください。
シーン別手続き例
健康保険/厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動届)
国民年金第3号被保険者関係届
雇用保険被保険者資格取得届