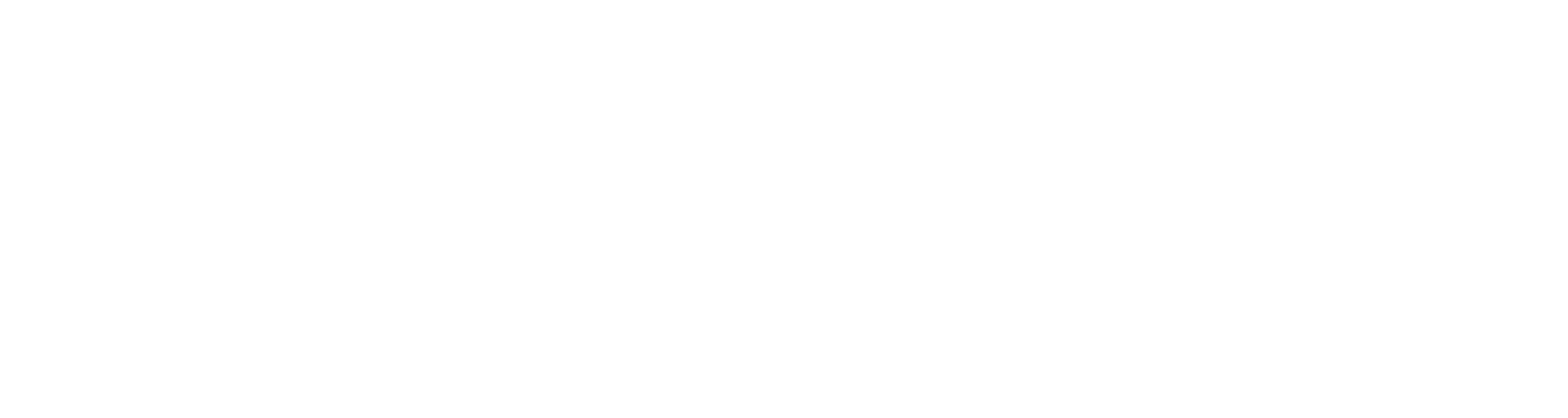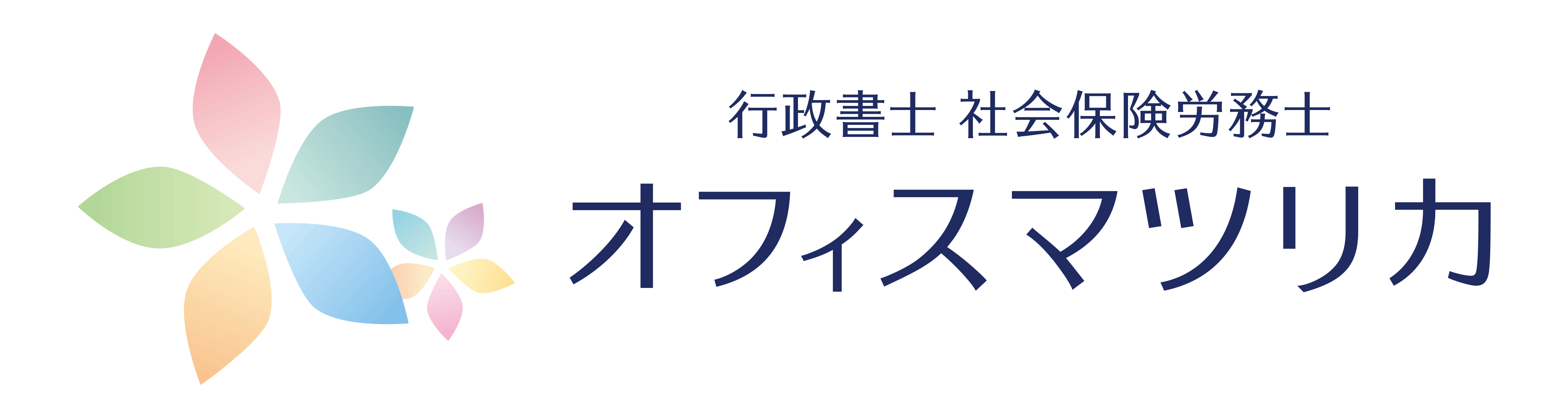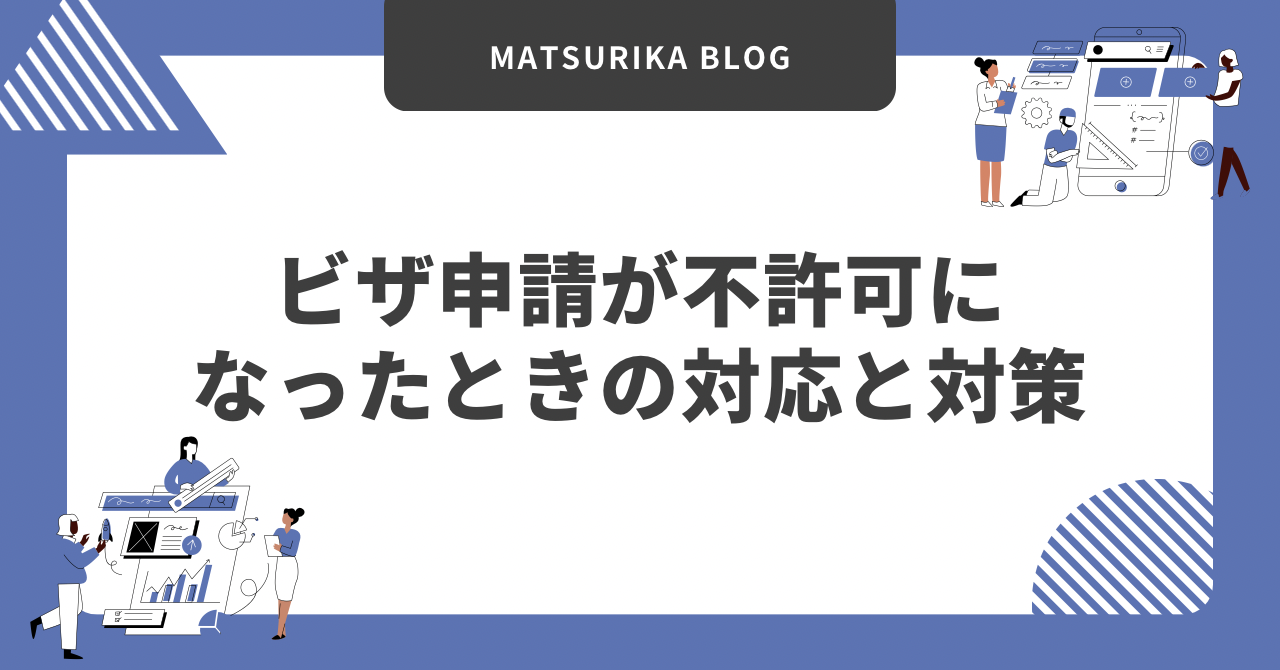「入管でビザ申請をしたが、不許可になってしまってどうしたらよいかわからない。絶対、許可が欲しいのですが、あきらめなければなりませんか?」というご相談をよくいただきます。
結論から言いますと、「しっかりと対策して再申請をすれば許可になるケース」と「再申請をしても、ほぼ許可の見込みはない(そもそも再申請できない)ケース」があり、どちらの結果になるかは、ほとんどの場合、再申請をする前の段階で分かることが多いです。
この記事では、思いがけずビザ申請が不許可になってしまった場合の考え方、とるべき対応について解説します。
ビザ申請が不許可になる主な原因
不許可の主な原因は、申請する在留資格の種類、申請の具体的内容のほか、申請人のバックグラウンド等により様々ですが、ほとんどの場合、次のケースのいずれかが原因となっていることが多いです。
よくある不許可理由
① 在留資格の許可要件を満たしていない
在留資格は、その種類によってそれぞれ許可要件が定められているところ、そもそもこの要件に該当していない状態で申請をしてしまったケースです。例えば就労系の在留資格では「仕事の内容の妥当性」や、「学歴または実務経験や資格等」が許可要件になっていますが、これらに該当していないと認められる場合には許可を得ることはできません。
② 申請人の素行が不良である
在留期間の更新や、在留資格の変更申請の場合は、申請人自身のこれまでの在留状況も審査の対象となります。
例えば、「犯罪による処分歴がある」「収めるべき税金を納めていない」「理由もなく、長期間にわたり現在の在留資格の活動をしていない。または認められていない活動をしている」「アルバイトの時間制限を守っていない」などは「在留状況が不良である」と評価され、その結果、許可が認められないケースも少なくありません。
③ 過去の申請内容と整合性が合わない事項がある
意外と軽く考えられがちですが、過去にビザ申請をしたことがある方については、そのときの申請内容と今回の内容について整合性がとれている(矛盾していない)ことも非常に重要です。
不許可原因との関係では、最も多いケースとして挙げられるのが学歴の相違です。例えば在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可要件の一つとして求められる「学歴要件(大学等の卒業)」において、過去に技能実習生として来日した際に入管に提出した申請書類では「最終学歴は高卒」となっていたのに対し、今回の申請では「大学卒」になっているケースです。
『自分の経歴であるにもかかわらず学歴を間違えるはずはない』と考えるのは自然ですが、技能実習生の在留申請の際には申請人以外の第三者(本国の送り出し機関等)が申請書類作成に関わっており、実は本人の知らないところで申請書類の内容が改ざんされているケースも少なくありません。
これに気が付かずに、技能実習修了から数年後、他の在留資格を取得するために「最終学歴を大学卒とする履歴書」や「大学の卒業証明書」を添付して申請をすると、入管は「過去の申請が高卒となっていたので、今回提出された大学卒という経歴は虚偽である可能性がある(=経歴に疑義ある。または信ぴょう性がない)」として不許可の処分を下します。
※時系列からみて、技能実習修了後に本国に戻り、その後に大学に入学・卒業したことが明らかなケースでは問題が生じることはありません。
④ 申請理由の説明が不足している(十分な説明を尽くしていない)
提出した申請理由書に記載した内容や、説明を補完する添付資料が不足しており、入管側にその意図や背景が伝わらずに不許可になるケースです。通常、これらの場合は審査の過程において「追加資料提出通知」というものが届き、説明に足りない点について再度資料を提出するというステップがありますが、この機会を与えられずにいきなり不許可とされてしまう場合もありますので注意が必要です。
不許可後に取るべき対応
不許可の具体的な理由を聞く
申請が不許可になる場合、申請先の入管でその具体的な理由を聞くことができます。
再申請をする可能性がある場合は、ここでの聴取内容がその後の結果を左右することになりますので「不許可の理由を残らず聞く」ことが重要です。
入管の担当者は不許可の理由のうち最も大きいもの(直接の原因となっているもの)を話しますが、その他の細かい事項についてはこちらから聞かないと教えてくれないことも多いです。ですので、理由を聞くときには「他に不許可の原因となっている理由はありますか?」などと話してみるのも有効です。
不許可の理由を聞くことができるタイミングは、在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請等の場合は、申請人に届く通知書に記載されている入管への出頭日(申請の結果をお知らせしますので〇月〇日〇時に入管に来てくださいと記載があります)、在留資格認定証明書交付申請の場合は不交付通知書が届いた後、任意のタイミングとなります。
特に、在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請の場合は外国籍の方である申請人本人が入管に行く必要があるため、日本語に不安がある場合は入管担当者の話す内容を十分に理解できる通訳者か、会社の人事担当者等が同行すると良いでしょう。
不許可理由を分析する
聴取した不許可の理由を分析し、再申請による許可の見込みについて判断します。
ある程度の判断基準として、不許可の理由となっている原因が上記「よくある不許可理由」のうち「①許可要件を満たしていない、②在留状況が不良である」場合は、再申請をしても許可の見込みはありません。
反対に、不許可の理由が「③過去の申請内容と整合性が合わない事項がある」や「④申請理由の説明が不足している」の場合はそれが悪質なものでない限り、再申請時に説明・立証をすることで許可となるケースも多いです。
再申請した場合の許可可能性を判断する
入管で不許可理由を聞いた際の担当者の話ぶり、感触、不許可理由の内容から、再申請をした場合に許可となる見込みがあるかについて総合的に判断します。実は、不許可理由の説明の際に入管の担当者から「これは再申請をしても厳しい」あるいは「〇〇を改善して再申請してみてください」などアドバイスをもらえることもあり、これらも判断の重要な要素となります。
弊所ではご自身で申請をして不許可になってしまった方からのご相談・ご依頼も多くお受けしておりますが、不許可理由の聴取に同行させていただいた方で、再申請をすることができた方については許可率100%となっています。
「100%」というと誇大広告のようにも見えますが、これは実はそうではなく、不許可理由の分析を適切に行ったことの結果です。すでにご説明したとおり、許可要件を満たしていない場合や、申請人の在留状況が極端に良くない場合などはそもそも再申請をしても許可は得られないので、残念ながら、その場合は弊所でもお手伝いをすることはできません。
しかしながら、それ以外の場合は不許可の理由に応じた適切な資料の用意・説明を行うことで対応可能です。
この「適切な資料・説明」が何かについて、不許可理由の聴取時における担当者とのやりとりが重要なヒントになります。
まとめ:不許可理由の分析は行政書士へ
以上、ビザ申請の主な不許可理由と、その対応について簡単にご説明いたしました。
いかがでしたでしょうか。不許可後の再申請については不許可理由の聴取と分析がとても大切だということがお分かりいただけたことと思います。
しかしながら、正確に不許可理由の分析をするためには各在留資格の許可要件や入管の審査要領等に関する知識のほか、「このケースには、この資料や立証方法が有効」といったような過去の実績から得られる経験が必要不可欠になってきます。
また、現在の在留期限の関係から再申請を急がなくてはならないため、不許可後の対応に時間をかけている時間がないことも多々あります。
弊所では、このような方のために「不許可理由の聴取同行」と「再申請手続」のサービスをご用意しております。
入管から不許可通知が届いて困っているという方は一度ご相談ください。
※ご自身のみですでに不許可理由を聴取済みの方からの再申請のご依頼もお受けしておりますが、その場合は再申請の対策が不十分になる可能性があります(入管担当者の説明の意図を正確に理解できていない場合や、聞き漏らし、あるいは自分に有利なように誤った解釈をしてしまうなど。)ので、極力、聴取前にご相談をいただければと思います。