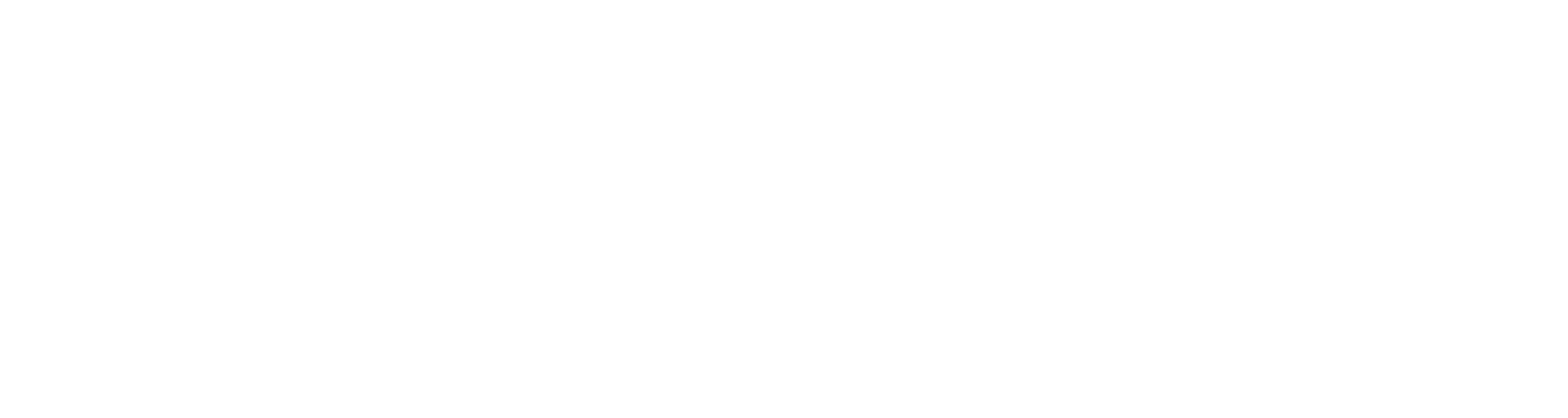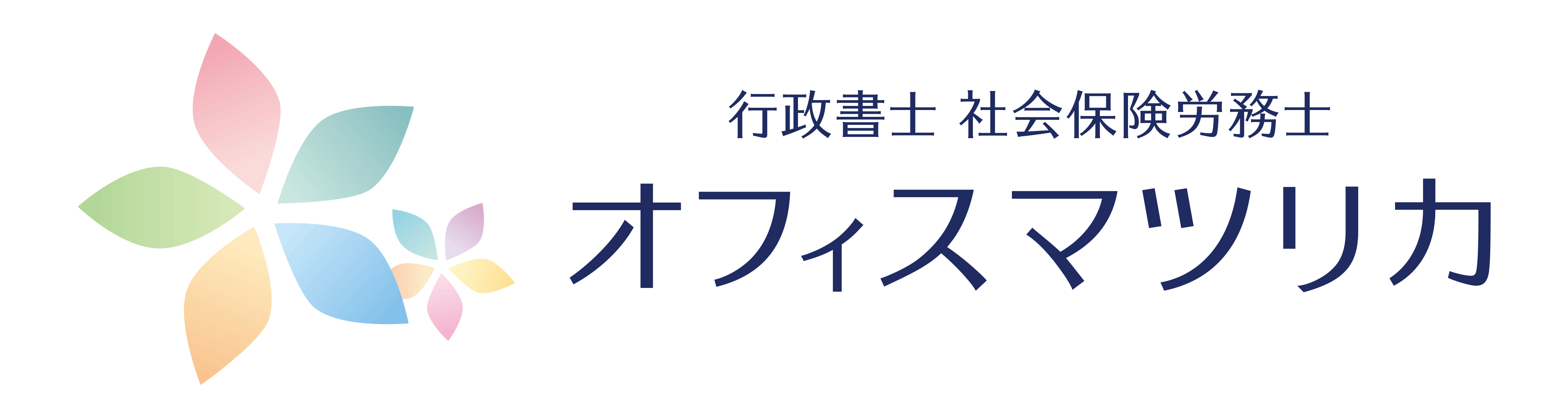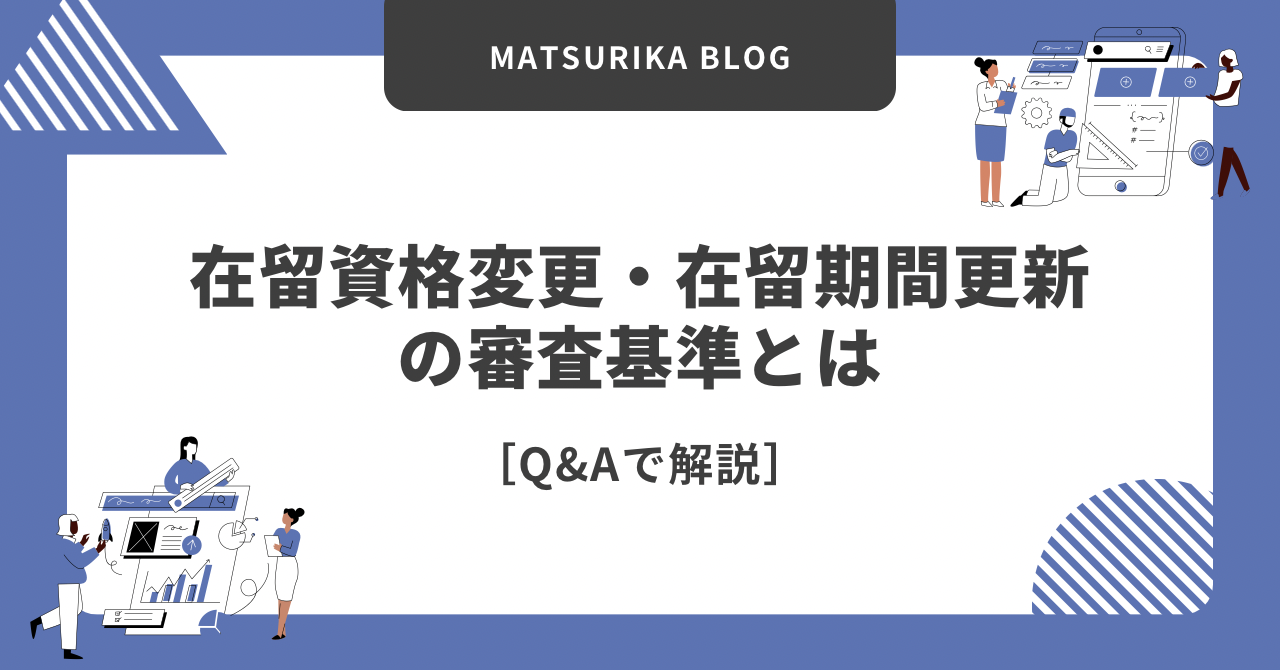在留資格変更・在留期間更新のガイドラインについて
「在留資格の変更や、在留期間更新の申請について、入管はどのような点について審査をしているのでしょうか?
何か決められているものなどがあれば教えてください。」
この質問にQ&A形式でお答えいたします。
- 在留資格の変更や更新は誰が許可を判断するのですか?
-
在留資格の変更や更新は、法務大臣が「相当の理由」があると認めた場合に許可されます。この「相当の理由」は、申請者の活動内容や現在の在留状況、在留の必要性などを総合的に考慮して決定されるとしています。実際の審査は、出入国在留管理局(入管)が担当しています。
- ガイドラインの内容はどのようなものですか?
-
入管庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可ガイドライン」には次の内容が記載されています。
- 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
- 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務等を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
- 「入管法別表に掲げる在留資格に該当する」とは何ですか?
-
在留資格はその活動の内容に応じて色々な種類のものがありますが、それぞれの内容について「この在留資格は、このような活動をするためのものです」といったような決まりが記載された表があります(入管法別表と呼ばれています)。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、「入管法別表第一の二の表」のなかで次のように記載されています。本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
つまり、在留資格の変更や、延長をする場合において、申請人となる外国人の方がこれから活動しようとうする内容が、この表の該当する在留資格の欄に記載されたものと合致することが必要で、これを「在留資格該当性」といいます。
- 「上陸許可基準への適合」とは何ですか?
-
上陸許可基準とはそれぞれの在留資格において「どのような条件に合致すれば上陸(入国)が認められるか」について定められたものです。「上陸の基準」ですから、この基準は外国人が日本に入国する際に求められるものですが、一部の在留資格については在留資格の変更や更新の申請時においてもこれに適合していることが求められます。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準は次のように定められています。申請人が次のいずれにも該当していること。
(一) 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を習得していること(略)。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
(二)申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
(三)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」として外国人を雇用する場合の考え方について具体例で教えてください。
-
実際に弊所で手続きをした事例です。
母国の大学で機械工学を専攻し、機械工学、NCプログラム、CAD実習等の科目を履修し学士号を取得した者が、輸送用機械器具製造を主たる事業とする会社に雇用され、月額報酬25万円(基本給)を受けて金属部品の設計や製図等の業務に従事するもの。
(解説)
①金属部品の設計や製図等の業務は「工学の技術若しくは知識を要する業務」に当てはまりますので、在留資格該当性があります。
②大学で機械工学を専攻し学士号を取得しており、関連する工学の知識を必要とする業務を行うものですので、上記の上陸基準において(一)のイに該当しています。
③月額の報酬額が基本給で25万円としているので、一般的にみて上記の上陸基準において(三)に該当しています。
- 現在の資格に応じた活動を行っていない場合はどうなりますか?
-
在留資格に該当性があって、上陸許可基準に適合している場合であっても、申請人が現在の在留資格に基づく活動を適切に行っていない場合は審査で消極的(不利)に評価されることがあります。
例えば、「留学」の在留資格で活動している留学生が退学をしたり、除籍された後、長期間にわたり正当な理由なく在留を継続している場合や、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働いていた方が退職し、その後転職することなく相当期間が経過していた場合などが該当します。 - 「素行の不良でないこと」とは何を指しますか?
-
退去強制事由に該当するような刑事処分を受けたことがあったり、不法就労をあっせんしていたりなどの行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。
- 「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する」とはどのような基準ですか?
-
自立かつ安定的な在留活動を行えるかについての判断基準です。具体的には、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その資産や技能などから見て、将来において安定した生活が見込まれることが求められています。
仮に、この基準に満たない部分がある場合でも、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断するとされています。
- 「適正な雇用・労働条件」とは何ですか?
-
申請者を雇用する際の労働条件が労働関係法規に適合していることが必要とされています。この場合の遵守すべき労働関係法規とは日本人を雇用する場合と異なるところはないため、通常の労務管理を行うことができていれば問題はないのですが、想定されるケースとして「外国人だからと他の日本人より安い賃金として雇用し、その賃金が最低賃金以下のものであること」などがあります。
- 納税義務はどのように評価されますか?
-
申請者となる外国人が納税すべき税金の納付を適切に行っていることが求められます。これら税金の未納や滞納がある場合には、在留資格変更または在留期間更新申請の審査時において不利に働きます。特に、未納額が高額であったり、相当期間に渡って滞納をしているなどの場合は悪質であると判断され、許可を得ることが難しくなります。
- 「入管法に定める届出等の義務」には何が含まれますか?
-
入管法では、外国人の在留資格や身分、雇用状況などに関する一定の事項について届出義務が課せられています。
これらの届出は、外国人の適正な在留管理を行うために必要なものであり、対象となる外国人本人や雇用主、関係機関に義務が課されています。
ガイドラインにおいては、外国人本人が行うべき届出について適正に履行されていることが必要とされています。義務付けられている届出の例- 住居地の変更届出(入管法第19条の9第1項)
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出(入管法第19条の10)
- 所属(契約)機関に関する届出(入管法第19条の16第2号)
- 配偶者に関する届出(入管法第19条の16第3号)
まとめ
在留資格の変更や更新許可の審査は、入管内部の審査要領や上記ガイドラインに沿って審査されています。
これらの申請を行う前にはガイドラインの記載事項を十分に確認し、不安な点があれば専門家にご相談をいただくことでスムーズな手続きが可能となります。しっかりと確認・準備を行い在留資格の変更・更新を成功させましょう。